研究室スタッフより
研究室のスタッフが、それぞれが専門としている研究について紹介しています。
教授・水野 亮 / Akira Mizuno(理学研究科理学専攻物理科学領域・大気圏環境変動研究室)
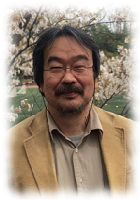 宇宙地球環境研究所に着任する前は電波望遠鏡を用いて太陽のような恒星が誕生する星間分子雲の研究をしていました。現在、水野研で用いているミリ波スペクトルの観測装置は、電波望遠鏡に用いていた高感度の超伝導受信機を地球の大気観測に最も適するように改良を加えたものです。現在は天文の観測時には観測の支障になっていた地球の大気を研究の対象としています。数百光年の彼方だけでなく、地球の近傍でもまだまだ私たちが理解できていない面白い現象がいっぱいあります。最近では太陽系外の惑星がぞくぞく見つかり、観測技術も日々進歩していますが、恒星が惑星の環境に与える影響が詳細に観測できるのは何と言っても我々が生きているこの地球と太陽系をおいて他にありません。自分で作った観測装置を使って、私たちが暮らしている地球の環境とその環境を変化させている要因を解明し、そうした研究を通して我々の地球が宇宙の中でどのように形成され、生命が誕生したのかをいっしょに考えてみませんか?
宇宙地球環境研究所に着任する前は電波望遠鏡を用いて太陽のような恒星が誕生する星間分子雲の研究をしていました。現在、水野研で用いているミリ波スペクトルの観測装置は、電波望遠鏡に用いていた高感度の超伝導受信機を地球の大気観測に最も適するように改良を加えたものです。現在は天文の観測時には観測の支障になっていた地球の大気を研究の対象としています。数百光年の彼方だけでなく、地球の近傍でもまだまだ私たちが理解できていない面白い現象がいっぱいあります。最近では太陽系外の惑星がぞくぞく見つかり、観測技術も日々進歩していますが、恒星が惑星の環境に与える影響が詳細に観測できるのは何と言っても我々が生きているこの地球と太陽系をおいて他にありません。自分で作った観測装置を使って、私たちが暮らしている地球の環境とその環境を変化させている要因を解明し、そうした研究を通して我々の地球が宇宙の中でどのように形成され、生命が誕生したのかをいっしょに考えてみませんか?
准教授・長濱 智生 / Tomoo Nagahama(理学研究科理学専攻物理科学領域・大気圏環境変動研究室)
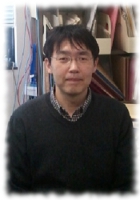 名古屋大学でミリ波電波望遠鏡を使った星間ガスの観測から星の誕生する過程を研究し博士学位を取得しました。その後、ポスドクとして過ごした国立環境研究所、そして現在の宇宙地球環境研究所では、ミリ波電波を使ったオゾン層の観測手法の研究と観測を行い、さらには近赤外線を使った大気中の二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスの地上からの観測手法の研究と観測をおこなっています。私たちの地球の大気は決して静的のものではなく、地球内外のさまざまな影響を受けて常に変化しています。多くの場合、変化の度合いはごくわずかですが、その様子を最先端の特徴ある(そして時には不具合と長く格闘することになる)観測装置により時々刻々と捉えることで、私たちの地球の姿を冷静にみつめることができればと思います。
名古屋大学でミリ波電波望遠鏡を使った星間ガスの観測から星の誕生する過程を研究し博士学位を取得しました。その後、ポスドクとして過ごした国立環境研究所、そして現在の宇宙地球環境研究所では、ミリ波電波を使ったオゾン層の観測手法の研究と観測を行い、さらには近赤外線を使った大気中の二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスの地上からの観測手法の研究と観測をおこなっています。私たちの地球の大気は決して静的のものではなく、地球内外のさまざまな影響を受けて常に変化しています。多くの場合、変化の度合いはごくわずかですが、その様子を最先端の特徴ある(そして時には不具合と長く格闘することになる)観測装置により時々刻々と捉えることで、私たちの地球の姿を冷静にみつめることができればと思います。
